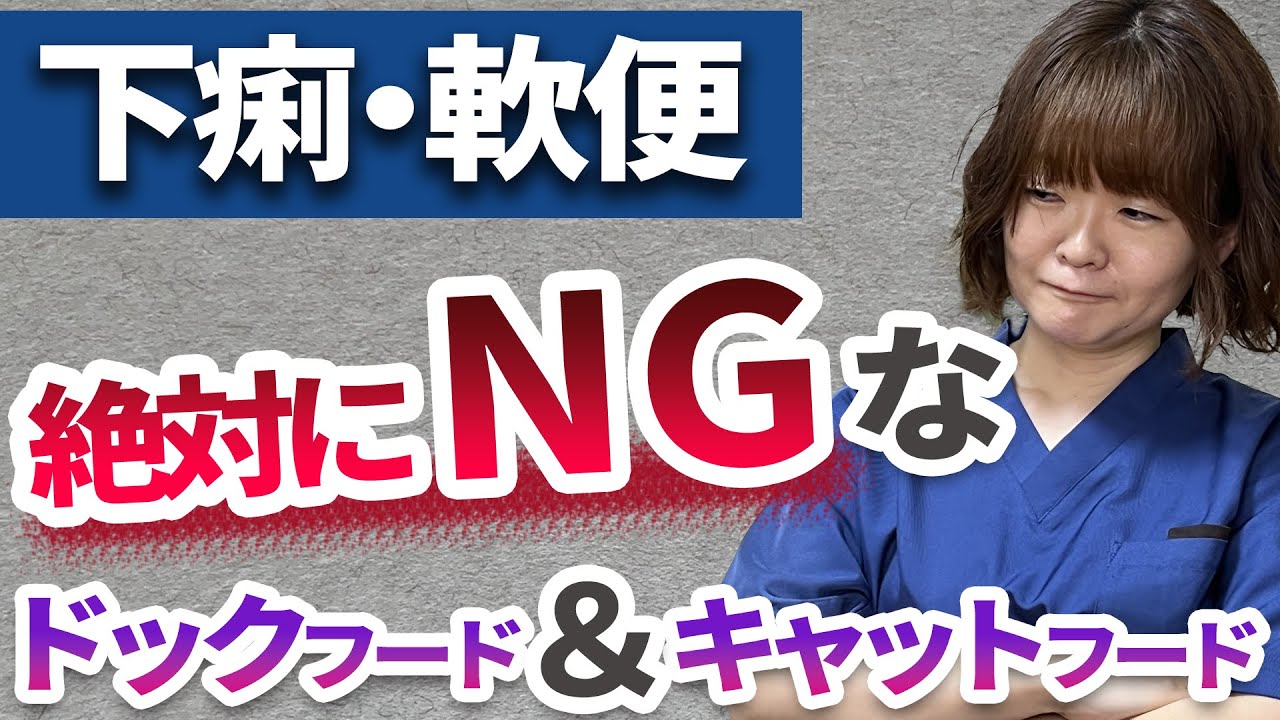「元気はあるけれど、うんちが柔らかいのが気になる」「毎日ではないけれど、軟便を繰り返している」など、ワンちゃんの軟便について、心配されている飼い主さんは多いのではないでしょうか?
今回は、犬の軟便の原因とそれぞれの改善方法について解説します。
食事が原因の場合に軟便のワンちゃんにおすすめのフードもご紹介していきますので、是非最後までご覧ください。
Youtubeでも下痢・軟便について解説しているのでぜひご覧ください。
犬のうんちが柔らかい原因は?

一口に軟便と言っても、原因は様々であり、原因によって対処方法は異なります。
まずは、どのような原因で軟便になるのか見ていきましょう。
食事量・水分量が多すぎる

食事量が多いと消化管に負担がかかり、きちんと消化しきれないことがあります。
また、水分摂取量が多過ぎる場合も腸で吸収できる水分摂取量を超えてしまうと便が柔らかくなってしまいます。
消化液が薄まってしまい、消化機能が低下することで軟便になっていることも考えられます。
食物繊維の量が体に合っていない
食物繊維は通常、便の嵩を増やし、排便を助けてくれる役割があります。
しかし、食物繊維が多過ぎる場合には、腸に負担がかかり、軟便になってしまうことがあります。
キャベツなど葉物野菜をおやつとして与えている場合には、水溶性食物繊維を多く摂っていることになります。
水溶性食物繊維は、便に水分を含ませる役割があり、便秘のワンちゃんには有効ですが、摂り過ぎると便の水分量が多くなりすぎて軟便となることがあります。
脂質が多すぎる

犬は人間に比べ、脂質の消化は得意な動物です。
しかし、高脂肪のフードは消化の負担になり、体質によっては軟便の原因になります。
食物アレルギー
フードやおやつの原材料にアレルギーの食材がある場合、便に影響が出ることがあります。
アレルゲンとなるのは主にタンパク質なので、肉、魚、大豆などタンパク質の多い食材のアレルギーが多いです。
しかしながら、野菜や穀物にもタンパク質は含まれるため、ほとんどの食材がアレルギーの原因になる可能性があります。
気候の変化
毎回、季節の変わり目に軟便になる場合は、自律神経の乱れによって腸の動きが悪くなることで引き起こされていることが考えられます。
子犬の軟便に多い寄生虫症

子犬は、母犬の胎盤や母乳から寄生虫に感染していることがあります。
ブリーダーのもとにいるときに、他の犬の糞便から感染することもあります。
軟便が続くので、糞便検査をしたら寄生虫が見られたということは多いです。
病気が隠れている
寄生虫症などの感染症のほかにも、膵炎や消化器疾患、慢性腎臓病、リンパ腫などの腫瘍など病気が隠れている場合も軟便の症状が出ることがあります。
犬の軟便の原因まとめ
・食事量・水分量が多い
・食物繊維の量が体に合っていない
・脂質が多すぎる
・食物アレルギー
・気候の変化
・寄生虫症
・その他病気
犬の軟便の対象法
まずは動物病院を受診しよう!

「軟便は食事のせいかもしれないから、食事を変えてみよう」と考える飼い主さんも多いのですが、今までご説明してきたように、食事が原因とは限りません。
かわいいわんちゃんのために、早く改善してあげたいと思うお気持ちは分かりますが、軟便を改善するためには、焦らず、原因は何なのか順番に検証していくことが大切です。
また、軟便は「元気があるから様子を見よう」と思われがちですが、感染症や消化管の病気が隠れていることもあります。
放っておくことで悪化する恐れもあるため、まずは改善方法を試みる前に動物病院を受診しましょう。
子犬では、症状が悪化しやすいため注意が必要です。
特に以下のような症状がある場合には、様子を見ずに早めに受診しましょう。
・軟便を繰り返し体重が減っている
・元気・食欲がない
・嘔吐など他にも症状がある
犬の軟便、お家でできる改善方法
病院を受診して、大きな異常もなく改善されたものの、軟便を頻繁に繰り返す場合があります。
そのような場合は、次の方法を試してみると良いかもしれません。
食事量と水分摂取量を見直す

食事量を1割程度減らしてみるだけで、消化管の負担が減り、軟便が良くなることがあります。
水分については、生きるために必要なものなので、飲み水を制限すべきではありませんが、「水分摂取が大切という情報を見たから」と言って食事に水やスープなどを加えている場合には、少し量を減らしてみましょう。
粗繊維の量が少なめなフードを選ぶ
今お使いのフードの保証成分値を見てください。
粗繊維の量が5%を超えるようなフードを与えていて軟便の場合、少し繊維の量が多いのかもしれません。
特にダイエット用のフードは粗繊維が多めに作られていることが多いです。
ダイエット用のフードを与えている場合には、通常のフードに戻すか、便の状態を見ながらカロリーはそのままに通常のフードとダイエットフードを混ぜて与えるのが良いでしょう。

脂質の少ないフードを選ぶ

現在食べさせているフードが低脂肪であれば、フードの脂質について見直す必要はありませんが、脂質が多いフードを与えている場合には、低脂肪のものに切り替えることで軟便が改善することがあります。
具体的には、乾物量で10%前後、多くても15%までのものを選ぶようにしてください。
軟便のワンちゃんは、脂質15%を超えるようなフードは避けた方が良いでしょう。
消化器用療法食を使うのも一案です!
このブログでは、基本的には動物性タンパク質が主原料として使用されている物の方が消化に良いとご紹介していますが、消化器用療法食は原材料に植物性タンパク質が多く含まれるものもあります。
療法食と原材料の考え方については、こちらの記事をご覧ください。
軟便が治らない場合は食物アレルギーの可能性も?
整腸剤の処方や食事の量・成分を見直しても改善されない場合には、食物アレルギーの可能性があります。
そのような場合には、再度、動物病院を受診し、アレルギーの食事や検査、治療について相談してみましょう。
アレルギーの場合の食事の選択や治療は、かかりつけの先生と相談しながら行うようにしください。
食物アレルギーと食事についてはこちらの記事でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
-
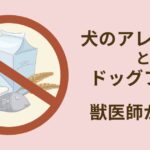
-
参考【獣医が選ぶ】アレルギーのある犬におすすめドッグフード5選を紹介!
フードと関係する疾患として、食物アレルギーがあります。 「アレルギー対策と言えば、グルテンフリー、グレインフリー」と思われている飼い主さんも多いですが、それは間違いです。 愛犬のアレルギーで悩む飼い主 ...
続きを見る
軟便気味のワンちゃんにおすすめのドッグフードは?

軟便のワンちゃんの食事として重要なことをまとめますと、次の通りです。
・脂質は乾物量で10%前後(15%まで)
・粗繊維は乾物量で5%まで
・主原料が動物性タンパク質(療法食を除く)
こうした特徴を持つフードの中で、おすすめのものを2つ紹介します。
どちらもお腹に優しいフードですので、原材料などワンちゃんの好みに合わせて選んであげてくださいね。
ナチュラルハーベスト おなかにやさしいフード
脂質8%(乾物量約8.9%)、粗繊維4%(乾物量4.4%)と低脂質で繊維の量も程よく含まれたフードです。
主原料には、魚(タチウオ、カツオ、イワシ)を使用しています。
フェリカス菌、ビフィズス菌を配合しており、腸内環境を整えることを考えたフードです。
人工の防腐剤・着色料・香料など、ワンちゃんの体に不要な物を使っていないという点でも消化に優しいと言えるでしょう。
おなかにやさしいフード | 株式会社バンガードインターナショナルフーズ (natural-harvest.co.jp)
犬猫生活 オールステージ用

脂質10%(乾物量11.1%)、粗繊維3%以下(乾物量3.3%)と脂質、粗繊維ともに控えめで、軟便のワンちゃんでも安心して与えることができます。
原材料には動物性タンパク質(牛肉、鶏肉、魚)を使用したフードとなっています。
乳酸菌と乳酸菌のエサとなるオリゴ糖が含まれており、腸内環境を整えることが期待できます。
合成添加物不使用ですので、消化に余計な負担をかけずに済みます。
-

-
参考犬猫生活ドッグフードはコスパが悪い?口コミ評価・成分・安全性を獣医師が徹底調査!
犬猫生活(旧レガリエ)は、高品質な国産ドッグフードとして、とても評判の良いフードです。 国産ドッグフードをお探しの方で、なるべく愛犬の健康に良いものを探している方にはおすすめのフードです。 獣医師に加 ...
続きを見る
軟便にはトッピングごはんもオススメ!

軟便には、脂質の少ないフードが理想ですが、脂質の少ないフードはどうしてもグラムあたりのカロリーが低くなる傾向があります。
また、タンパク質が中程度のものが多いため、育ち盛りの子犬には少し物足りないことも考えられます。
タンパク質が豊富で食いつきが良くなるウェットフードやフレッシュフードを取り入れることで、充分な栄養を摂ることができます。
軟便のわんちゃんでも安心してトッピングできるフードをご紹介します。
ウェルフードッグフード
一般的にウェットフードは動物性タンパク質の含有量がドライフードに比べ多いです。
タンパク質の補給にはピッタリですが、その分脂質が多くなる傾向があります。
健康なワンちゃんであれば問題ないものの、軟便の子には脂質が多過ぎるものもあります。
ウェルフードッグフードは、大分するとウェットフードですが分類されます。
しかし、脂質3.7%(乾物量14.9%)、粗繊維0.4%(乾物量1.6%)と低脂質で繊維の量も少ないため、軟便のワンちゃんでも安心してトッピングに使うことができます。
はぴねす乳酸菌と呼ばれる乳酸菌を配合し、お腹の調子に配慮しています。
香料・保存料など一切使用していないので、その点でもお腹に優しいフードといえるでしょう。
また、総合栄養食なので、ドライフードとの割合を気にせず使うことができる点もオススメです。
ウェルフードッグフードの調査記事はこちら
フレッシュフードの調査記事はこちら
-

-
参考【獣医が選ぶ】犬におすすめの手作りごはん-フレッシュフード-7選!
日経トレンディの「2022年ヒット予測ベスト30」に堂々の18位に選ばれ、注目を集めているフレッシュフード! 2023年1月にはココグルメさんがテレビCMをするなど、ますます利用される方が増えそうです ...
続きを見る
まとめ
今回は犬の軟便について原因と改善方法、また、軟便気味の子のフード選びについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか?
軟便は食事が原因の場合も多くありますが、病気なども隠れている場合があります。
愛犬の軟便でこまったらまずは動物病院を受診するのが良いでしょう。